仕事を辞めるときは、保険証が変わります!!
社会人経験の浅いあなたは、自分で保険料を納めて保険証を持ち始めてからも、日が浅いですよね。
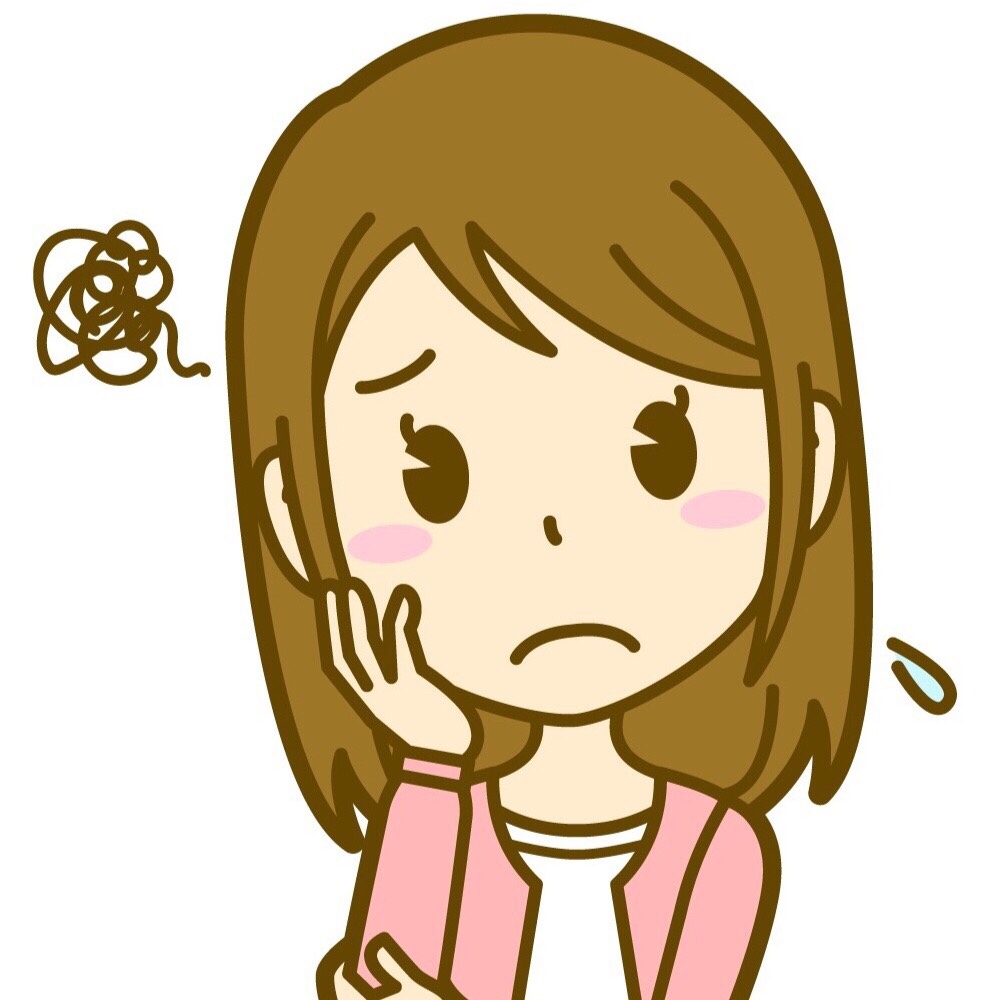
保険証の切り替え、そういえば初めてだ!
手順とか全然わからない!

やり方を間違えると、保険が使えなくて実費負担になることもあるよ!
きちんとやり方を知っておこう!
この記事では、
辞める会社の保険証はいつまで使える?
次の保険証はどんなタイプになる?
保険証の切り替え方
この3つを詳しく説明します。
切り替え方を間違えると、保険が使えずに多くのお金を払う必要があることも!
こちらをしっかり読んで、正しいタイミングで保険証を切り替えましょう。
辞める会社の保険証はいつまで使える?

辞める会社の保険証は、退職日まで使えます!
通常は、退職日に保険証を返却します。
最終出勤日と退職日が異なる場合はいつ返却する?
有給休暇を消化してから退職する
退職日を月の末日などキリが良い日にしたので、自分のお休みの日と重なる
このような理由で、『最終出勤日と退職日が異なる!』という場合もありますよね。
通常は、退職日まであなたが保険証を持っておきます。
保険証のためだけに辞めた会社に出向いて返却したり、郵送などで返却したりします。
郵送などで返却する場合は、『簡易書留などの記録が残る方法で送ってほしい』と指示されることがあります。
勝手に自己判断で送らず、まずは電話で連絡して指示を仰いでください。
「最終出勤日に保険証を返してほしい」と会社から指示される場合もあります。
退職日を過ぎてもあなたが保険証を使うことがないように、早めに会社側で預かっておきたい
あなたが保険証を郵送する手間を省く
という目的で、最終出勤日に返却するように指示しています。
あなたが「退職日を過ぎたら保険証が使えないことは知っている。こちらから郵送して返却することは構わない。」と伝えれば、退職日まで保険証を持っておくことはできますよ。
保険証を自分で破棄してもいい?
退職して保険証が使えなくなった際は、自分で破棄してはいけません!
保険証は、健康保険組合に返却することが義務付けられています。
必ず返却しましょう!!
退職日を過ぎたのにあなたの手元にある場合は、直接返しに行くか郵送でもOKか、会社の方に尋ねてみましょう!
辞めた後の保険証はどう変わるの?

保険証が変わりますが、新卒のあなたには4つのパターンがあります。
任意継続被保険者制度に加入する
親や兄弟の扶養に入り、親や兄弟の会社の健康保険に入る
国民健康保険に加入する
1つずつ説明します!
次の会社にすぐ転職する場合
会社を退職した翌日から次の会社に転職する場合は、次の会社の保険に入ります。
会社の方が手続きをしてくださるので、あなたが手続きしなければいけないことはありません!
任意継続被保険者制度に加入する場合
任意継続被保険者制度とは、『会社を辞めた後も、会社の健康保険組合に所属し続ける』という制度です。
会社に在籍している際は、あなたと会社側が保険料を半額ずつ払います。
退職した後は、会社側は保険料の負担をせず、あなたが保険料を全額支払います。
任意継続被保険者になるには、
「健康保険の被保険者期間が退職の日までに継続して2ヶ月以上あること」
「2年間を限度として加入すること」
という条件があります。
詳しく知りたい方はこちらの協会けんぽのホームページを確認していただくか、もしくは加入している健康保険組合に確認してください。
「国民健康保険の方が保険料が安くなると思われる人には、任意継続の制度を紹介しない」と決めている会社もあります。
新卒採用されたばかりのあなたの場合、初任給からほぼお給料は変わらず、扶養している家族もいない場合がほとんどですよね。
その場合は、任意継続より国民健康保険の方がお得なことが多いです!
任意継続を検討している際は、自分から会社の総務など担当の方に相談してみてください。
親や兄弟の扶養に入り、親や兄弟の会社の健康保険に入る場合
新卒採用されたばかりのあなたは、1年間の収入もまだ少ないですよね。
そんな場合は、親や兄弟などの扶養に入れるかもしれません!
扶養に入るためには、
「主として被保険者に生計を維持されている3親等以内の親族であり、年収130万円未満(60歳以上や一定の障害者は180万円未満)であること」
という条件があります。
これまでの給与明細や、退職した後でもらえる源泉徴収票で確認してみましょう。
親や兄弟の扶養に入ることができる場合は、新しく加入する健康保険組合から書類をもらい、記入する必要があります。
加入する組合によって書類や準備するものが違います。
詳しくは、新しく入る保険組合の担当の方に確認してください。
基本的には、あなたを扶養することになるご家族の方に、保険組合の担当の方への確認をお願いします。
扶養することになるご家族の方が手続きをすればOK、という場合が多いです。
国民健康保険に入る場合

これまで説明した3つに該当しない場合、国民健康保険に入ります。
国民健康保険に入る方が一番多いですよ!
お住まいの地域の役所に行き、国民健康保険の窓口に行きましょう。
持参するものはこちらです。
マイナンバーを証明するもの(マイナンバーの通知カード、写真入りのマイナンバーカードなど)
キャッシュカードか通帳(口座振替で納付したい場合)
健康保険の資格の喪失日がわかる書類は、この中の1つがあればOKです。
社会保険資格喪失証明書
離職票(ハローワークに行く前に役所に行く場合。ハローワークで提出が必要なので、確認後に返却してもらえます。)
退職証明書(形式は任意ですが社印などが押印してあるもの)
源泉徴収票(退職日が記載されているもの)
担当の方に、持参した書類を提出して、その場で渡された書類に記入すれば終わります。
その日に保険証が交付されて持ち帰れることが多いです!
病院には滅多に行かないから、保険に入りたくない!

「会社では健康保険料がお給料から天引きされていたから、保険料を収めていた。
でも自分は病院にほとんど行かないので、仕事をしていない期間は健康保険に入りたくない!」
このような場合、どうすればいいのでしょうか?
日本では『国民皆保険制度』という制度を取り入れています。
国民全員がなんらかの健康保険に入る必要がある、という制度です。
国民健康保険への加入資格があるにもかかわらず加入の手続きをしない人に対しては、法律で決められた罰則はありませんが、各市町村が10万円以下の過料を行う規定を設けることができる旨が定められています。
偽りや不正により保険料を免れていた場合は、その金額の5倍を過料される事もあります。
つまり、本来は国民健康保険に加入するべきところを、加入していない場合、市町村から罰金のようなものが取られる場合があるんです。
「病院に行きたいと思ったときに、国民健康保険の手続きをしたら入れるよ〜」なんて話を聞いたことがあるかもしれません。
国民健康保険は『原則として退職後14日以内に加入する』必要があります。
病院に行きたいときに加入するのは、NGです!
しかし、退職後14日を過ぎても、手続きに行けば加入することができます。
「必要な書類が手元に揃わず、退職後14日以内に間に合わない」というケースもあるので、柔軟に対応してもらえることが多いです。
保険料は、退職した翌日からさかのぼって支払う事になります。
退職後すぐに健康保険に加入しても、退職後から期間をあけて健康保険に加入しても、あなたが負担する金額は同じです。
退職から国民健康保険の加入までの期間をあけすぎると、一気に何十万円も保険料を払う必要があることも!
最大2年間分の保険料をさかのぼって支払うことになるので、注意してくださいね。
次の会社に転職するまで期間があく場合は、国民健康保険にすぐ加入しましょう!
任意継続制度を使う、家族の扶養に入り家族の会社の社会保険への加入するなど、他の方法で健康保険に入った方がお得な場合は、そちらを利用しましょう。
何らかの健康保険には、加入する義務があります!!!
★まとめ★
健康保険には必ず入らないといけない
健康保険に入らない場合、過料を支払う可能性がある
退職してすぐ保険に加入しても、病院に行きたいと思った時に保険に加入しても、あなたが負担する金額は変わらない
新しい会社に入ったとき、前の保険証はいつまで使える?

新しい会社に入社するときは、仕事をしていなかった期間に入っていた保険から脱退して、新しい会社の健康保険組合に入ります。
新しい会社の健康保険組合に入る際に、仕事を辞めていた間に使用していた保険証は、『新しい会社の入社日前日まで有効』です。
有効期限が記載されている保険証の場合は、「新しい会社の入社日前日まで有効」が優先されます。
国民健康保険の保険証には有効期限が記載されているので、注意してくださいね。
辞めた会社の保険証を返却したときと同様に、仕事をしていなかった期間に使っていた保険証も、返却する必要があります。
その際も、電話で一度連絡して、どのような方法で返せば良いか、確認をしましょう!
仕事を始めると、仕事を辞めていたときのように役所の窓口などに出向くことが難しいので、郵送でも良い場合が多いです。
どのような方法で送れば良いか、一旦確認しましょう。
健康保険組合に確認してから行動しよう!

すぐにできること、健康保険組合に確認すべきことはわかりましたか?
所属する健康保険組合によって手続きが異なる場合が多々あるので、自己判断で行動するのはNGです!
これを読んで自分でできることはすぐに行動して、健康保険組合に確認すべきことは確認しましょう!
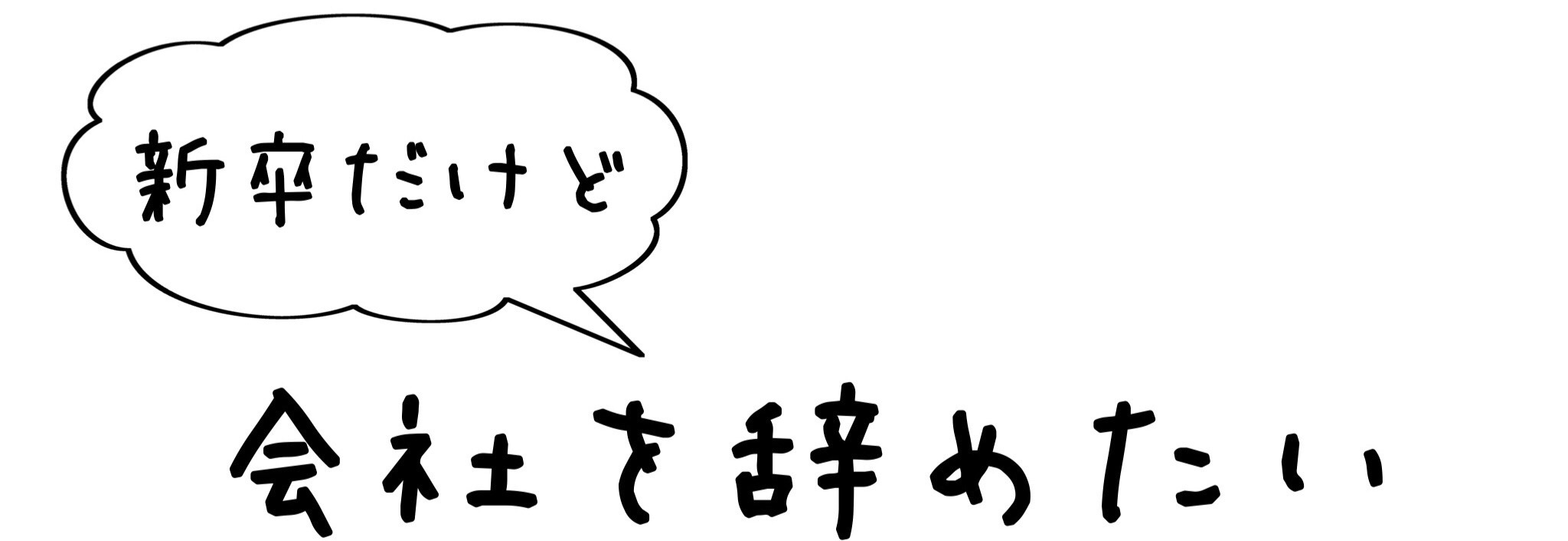
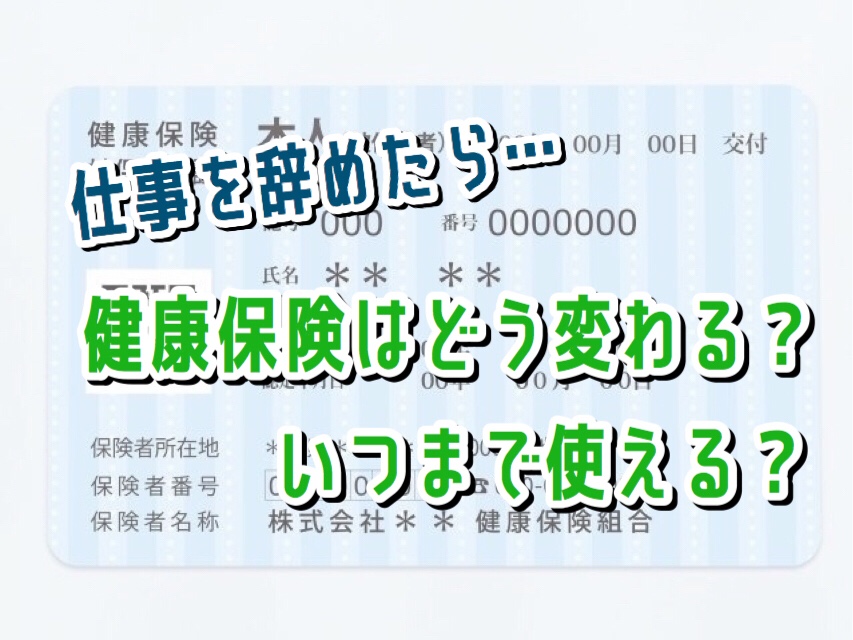
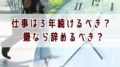

コメント